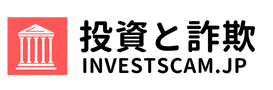生成AI技術の急速な普及とともに、「AIを使えば簡単に稼げる」という甘い言葉で消費者を勧誘する悪質なAIスクールが急増している。ChatGPTブームに乗じた新手の投資詐欺として、消費者庁や国民生活センターも注意を呼びかけている状況だ。
目次
SNS広告に潜む罠「無料セミナー」の裏側
「AIで副業、月収100万円も夢じゃない!まずは無料セミナーへ」——こんな広告をYouTubeやInstagramで見かけた経験はないだろうか。実際に参加した被害者の証言によると、これらの無料セミナーは巧妙に仕組まれた詐欺の入り口だという。
個人ブログ「白桃鷲@ASD&HSP(HSS型)の優しくせっかちで心理描写強めのエッセイ@時々、福梟(長)」(noteプラットフォーム、2025年2月27日投稿)によると、YouTubeで見かけた「無料AIセミナー」に参加した体験談として、「セミナー自体は基礎的な内容でしたが、その後4日間連続で『約15万円のコースに入らないと特典がもらえない』というメールが届いた」と報告されている。
セミナーの手口は巧妙だ。まず無料で基本的なAI活用法を教え、参加者の期待を高める。その後「本格的に稼ぐには有料プランが必要」「今日中に決めないと特別価格は適用されない」などと畳み掛け、高額な契約に誘導する。
100万円の受講料、内容は「YouTubeレベル」
AI業界で情報発信を行うMichikusa株式会社のusutaku氏は、自身のnote(2024年8月22日投稿「誰も騙さずに、AI講座を売った。〜本当にクソな生成AI業界に喧嘩をふっかける〜」)で衝撃的な実態を明かしている。「視聴者から『〇〇というスクールは月額何十万円〜何百万円するんですが、どう思いますか?』的な問い合わせが増えてきています」と述べ、実際に入会した人からは「入会してみたけど無料でも学べるような内容ばかりだった」「AI FREAKさんの無料動画の方がよっぽどためになりました」という声が多数寄せられていると報告している。
また、AI FREAK氏も自身のnote(2025年1月2日投稿)で「視聴者から『100万円近くスクール代がかかる』という相談を去年はよくいただきました」と明かし、「入会した人から『無料でも学べるような内容ばかりだった』という相談を多くいただきました」と業界の実情を暴露している。
この点を実際に複数のAIスクールの立ち上げにかかわった講師経験者A氏に話を聞いてみたところ、なるほどと思わせる回答を得たので紹介したい。「実はAIスクールには本当にパソコンを触ったことがない人も受講してくるんです。動画講習ではそういった本当の初心者でもわかるように動画講座を用意して、実際に質問なども受け付けるんですが、パソコンでコピペができない人、セカンドモニターにつないだことがない人、Gmailも持っていない人もいます。」とリテラシーの低さを嘆く声もある。またA氏は続ける。「初歩的な講座の内容はyoutubeで見せるスゴイ成果ではなないものから始まります。いきなり自動で記事を書き上げるなどの内容ではありません。その積み重ねで5000文字の記事が一瞬で作成できる自動化ワークフローを構築できるんですが、そんな内容は上級者向けです。高すぎる期待値を抱いている受講者側の問題もある気がします。」
そういわれるとそんな気もしてくる。だがこうした期待値と現実のギャップ以前に、振り込んだお金が返ってこない、実際に講義をしてもらえないというトラブルも発生しているようだ。これは明確に詐欺だといえるだろう。多くのプレイヤーがAIスクール事業に参入しているからこそ、こうしたトラブルが発生しているといえる。
詐欺業者が狙う心理的弱点
なぜこれほど多くの人が高額なAIスクールに騙されるのか。専門家は、以下の心理的要因を指摘する。
FOMO(取り残される恐怖): 「AI時代に乗り遅れたくない」という焦り 技術への過度な期待: 「AIがあれば誰でも簡単に稼げる」という思い込み 副業への関心: 物価高や将来不安から副収入を求める心理
「AIハマってみた」のnote(2025年5月10日投稿)では、「ChatGPTや画像生成AIは、誰でも無料で使える強力なツール」だが、「知識ゼロの初心者にとっては『難しそう』『触り方が分からない』という不安があり、そこに『教えますよ』と近づく業者が現れる」と分析している。
見分けるポイントは「誇大広告」と「不透明な料金体系」
悪質なAIスクールには共通する特徴がある。前述の「AIハマってみた」記事では、以下のような危険な兆候を挙げている:
危険な兆候
- 「月収30万稼げる」などの甘い文句が多い
- 具体的なカリキュラムや成果物が見えない
- ChatGPTの使い方を教えるだけで月5〜15万円を請求
- 運営会社や講師の情報が不透明
国民生活センターの情報(各種相談の件数や傾向ページ)によると、情報商材に関する相談では「購入するまで内容がわからないため、広告や説明と違い、あまり価値のない情報だった」というケースが多いとされている。
だが実際、複数のAIスクールで講師を務める講師に話を聞くと、教える営業方法や実践方法を実行せずに、稼げないと嘆いたり、動画講座や質問相談室を利用せずに不満を述べる購入者もいるという。AIスクールが教えるAI美女でSNSをバズらせる、であったり、ライターとして稼ぐという稼ぎ方は競争が激化しているのも事実。営業ノウハウや地道に教わったことを実行し、そこから差別化を図る努力をしないと稼げないという厳しい現実もあることだろう。
行政機関の対応状況
消費者庁は2024年に「最初に1万円程度の情報商材を消費者に購入させ、その後に執拗な電話勧誘により著しく高額な情報商材を購入させる事業者4社に関する注意喚起」を発表。情報商材を巡るトラブルが深刻化していることを受け、監視を強化している。
国民生活センターも「情報商材」に関する特設ページで注意を呼びかけており、「簡単に高額収入を得られることはありません」「安易に信用して事業者に連絡しないでください」と警告している。
被害に遭った場合の対処法
もしAIスクール詐欺の被害に遭った場合、以下の対応を取ることが重要だ。
- 証拠の保全: 広告のスクリーンショット、勧誘メール、契約書、決済記録などを保存
- 相談窓口への連絡: 消費者ホットライン「188」に相談
- クレジットカード会社への連絡: クレジット決済の場合は即座に連絡
- 法的措置の検討: 悪質な場合は弁護士に相談
クレジット・リース被害対策弁護団のサイトでは、情報商材被害について「販売業者の勧誘行為は違法であり不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求を主張することが考えられます」と法的対処法を解説している。
AIスキル習得の正しい道筋
AIスキルの習得自体は価値のある投資だ。ただし、高額なスクールに頼る必要はない。前述のusutaku氏も「AI技術は確実に社会を変革していますが、その学習に高額な費用は必要ありません」と指摘している。
推奨される段階的アプローチ:
第1段階: 無料リソースの活用(ChatGPT公式サイト、YouTube、書籍) 第2段階: 低価格教材での基礎固め(Udemy講座など数千円〜数万円程度) 第3段階: 実践での経験積み(個人プロジェクト、小規模副業案件)
消費者が取るべき対策
AIブームに便乗した詐欺から身を守るため、消費者は以下の点に注意すべきだ。
- 「簡単に稼げる」という甘い言葉に惑わされない
- 契約前に冷静な判断期間を設ける
- 運営会社や講師の実績を事前に調査する
- 異常に高額な料金設定のスクールは避ける
- 被害に遭った場合は速やかに専門機関に相談する
AI技術の進歩は止まらないが、その学習において消費者が悪質業者に騙される必要はない。正しい情報と冷静な判断により、適切なAIスキル習得の道を歩むことが重要だ。
【参考文献・出典】
- note「誰も騙さずに、AI講座を売った。〜本当にクソな生成AI業界に喧嘩をふっかける〜」(Michikusa株式会社、2024年8月22日)
- note「『ai副業で100万円を簡単に稼ぐ方法!』は詐欺なのか。」(AI FREAK、2025年1月2日)
- note「【実録】YouTubeの怪しいAIのWebセミナー参加part.2」(白桃鷲、2025年2月27日)
- Yahoo!知恵袋 SHIFT AI関連投稿
- romptn Magazine「SHIFT AI詐欺?怪しい?無料セミナーの評判・口コミを徹底調査!」(2025年8月)
- note「【AIスクール詐欺!!】ちょっと待って!初心者が騙されないためのチェックリスト」(AIハマってみた、2025年5月10日)
- 国民生活センター「情報商材(各種相談の件数や傾向)」
- 消費者庁「情報商材販売事業者4社に関する注意喚起」(2024年)
- クレジット・リース被害対策弁護団「情報商材被害」