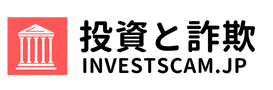目次
AIが下した冷酷な判定「銀行経営は失格」
2025年6月26日のスルガ銀行株主総会で、日本の株主総会史上初とも言える「AI活用経営分析」による経営陣批判が展開されました。入場券番号147番の株主は、Microsoft Copilotやその他複数のAIツールを駆使して同行を客観的に分析し、加藤社長の経営手腕を痛烈に批判しました。(写真はスルガ銀行株主総会後の被害者団体によるデモ行進。)
AIが解き明かした「6年半解決しない本当の理由」
この株主がAI分析で最も重要視したのは、なぜアパマン問題が6年半も解決しないのかという根本的な疑問でした。AIは以下の構造的問題を指摘しました。
問題1:戦略的曖昧さによる責任回避
AIはシェアハウスは一括解決したのに、アパマンは「個別事情が多様」として個別対応に固執する姿勢を「戦略的な責任回避」と断定しました。
「シェアハウスでは裁判所が「常習的な不法行為責任」を認定したのに対し、アパマンでは個別の事情が多様であるため、銀行は一律の責任を否定しています 。この法的・戦略的なアプローチが被害者団体との対立の根源になっています。銀行はアパマン問題での責任について、十分に対応していると認識しているものの、被害者団体は、銀行の姿勢を責任転嫁と見なしています」
問題2:短期利益至上主義の継続
AIは業務改善命令で「短期利益主義からの脱却」を掲げたにも関わらず、実際の対応は真逆だと断じました。
「スルガ銀行の今までの対応は被害者への徹底的な対応よりも、銀行の財務的損失を回避することを優先しており、これは、根本的な企業文化の変革がなされていなかったことを示唆しています。」
問題3:「隠蔽」や「先送り」の継続
最も深刻な指摘は、表面的な謝罪の裏で隠蔽体質が継続しているという分析でした。
「損失を表面化させないための手段として、遅延損害金や未収利息のカット、任意売却による債権回収を優先したことは、不正の根本原因を解決するのではなく、一時的な対処に留まっています 。この姿勢は、不正行為の責任を曖昧にし、過去の「事なかれ主義」や「情報の断絶」といった企業文化の継続に繋がっています。」
そして、AIはスルガ銀行の不正融資に対する取り組に対して以下のようにも評価していました。
対外的な信頼の喪失: 金融庁からの報告徴求命令や国会での問題提起は、現社長の対応が外部からの信頼を得られなかった結果です 。信頼を失った金融機関が持続的に成長することは極めて困難であり、現社長の対応は将来的な成長の芽を摘んだと言えるでしょう。したがって、従来の対応は、短期的な財務損失の表面化を回避した点では功績があったかもしれませんが、組織の信頼性、倫理性、および持続可能性という、より本質的な価値を大きく損なった失敗であると評価します。
「感情を入れずにクリアな回答」AIの客観性を武器に
この株主は営業利益1兆円超の大企業の新規ビジネスにおける事業戦略策定に従事する「パラレルワーカー」で、IT系AI関連部署での経験を持つと自己紹介しました。「AIは感情も入らずに、すごくクリアな回答をしてくれる」として、以下の資料をAIに読み込ませて分析を実行しました。
AI分析に使用した資料
- 第三者委員会報告書
- 監査役責任調査委員会報告書
- 取締役等責任調査委員会報告書
- 投資用不動産融資に係る全件調査報告書
- IR決算発表資料
AIが暴いた「利益構造の欺瞞」
AIの分析で最も注目すべきは、同行の利益構造に対する痛烈な指摘でした。4期連続増益を誇る同行の実態を、AIは以下のように喝破しました。
見せかけの成長の正体
「不良債権処理が一段落したことで、貸倒引当金戻入益が創出しているという過去の負の遺産を清算した結果である。実態的にはポジティブなんですが、新たな事業成長によるものではないということで疑問が投げかけられています」
不正利益の継続享受
さらに深刻な指摘は、同行が今でも過去の不正融資から利益を得続けているという分析でした。
「不正の過去の金利収益において利得することができているという点で、これがまた大きな収益源の一部となっています。これは過去の業務と紐づけられた収益基盤が依然として当社の主力とされていることを意味しており、本来であれば精査されるべき遺産である」
金融庁報告徴求命令の「真の意味」をAIが解読
株主は、なぜ金融庁が今になって報告徴求命令を発出したのかという根本的な疑問をAIに投げかけました。その回答は、表面的な理解を超えた深い洞察を含んでいました。
「金融庁の報告徴求命令は、スルガ銀行が問題の解決において十分として社会的な要請に応えきれていないという強い懸念であると受け止めるべきです。銀行が自身の不十分なプロアクティブな対応を通じた解決提案を認めたことは、確実に問題があったことを自覚している証拠である」
監督当局の限界認識
AIは、金融庁自体の監督責任についても言及しました。
「金融庁の監督では、早期発覚時の透明な報告、独立した調査機関の設置の検討と内部統制機能の評価、改善策での統制機能の十分性評価、財務への措置などが求められています。これらの要請は当局として懸念を抱いていることを強く示している」
白塗り改ざん問題への深い洞察
総会で新たに浮上した「白塗り改ざん」問題についても、AIは鋭い分析を提示しました。株主は、この問題をコンプライアンス体制の根本的欠陥の表れとして位置づけました。
組織的隠蔽の証拠
20件以上で確認された白塗り改ざんについて、株主は「これは2018年の業務改善命令受領後も続いている。コンプライアンス体制が全く改善されていない証拠」と指摘しました。
加藤社長の「リーダーシップ欠如」をAIが断罪
AIは加藤社長個人の経営能力についても容赦ない評価を下しました。
就任の意味と現実のギャップ
「加藤社長が経営陣から就任してきた点は問題の重大さを示すということで評価することができます。ただその認識にも関わらず、何も進展が無かったことは、社長としてのリーダーシップの欠如、根本的な問題解決に対するコミットメントの不足であると言えます」
表面的対応への警告
AIは、現在の対応が本質的な解決ではなく、むしろ問題を深刻化させていると警告しました。
「これはあくまで短期的かつ結果論的な運営の成果であり、これを持って全体戦略の対応成功ということはできません」
AIが提示した「根本的解決策」の衝撃
この株主のプレゼンテーションで最も注目すべきは、AIが導き出した具体的な解決策でした。単なる批判にとどまらず、建設的な提言として以下を提示しました。
集団調停への積極対応
「集団調停の場において裁判所の要請に対して迅速に対応する。そして責任が認められる可能性が高い事案については、積極的に協議を進め、合意に努めなさいということを提案しています」
早期解決フレームワークの問題点
株主は、同行が提示している「早期解決フレームワーク」についても鋭い質問を投げかけました。同行が第2段階で2件のみ関与を認めていることに対し、「他の約600件について、この2件と同様の検討を今までしてきたのでしょうか」と問い詰めました。
この質問は、同行の「個別対応」方針の根本的な矛盾を突いたものでした。もし本当に個別検討しているなら、2件以外にも関与が認められるケースがあるはずだという論理です。
「不正はあったが不法ではない」論理の破綻
総会の質疑で最も白熱したのは、同行の基本姿勢をめぐる議論でした。株主からは以下のような厳しい指摘がありました。
「不正があったことを認めているにも関わらず、裁判所から一括の不法行為が認められてない、法的構成要件が認められないなら、責任を負うつもりはないと、スルガ銀行は言ってるわけです」
この指摘は、同行の「不正≠不法」という論理構造の根本的な問題を突いたものでした。組織的不正を認めながら、法的責任は個別判断とする姿勢への疑問を提起しました。
企業文化変革の必要性
株主は、この問題が単なる法的技術論ではなく、企業文化の根本的変革が必要な問題だと指摘しました。
「不正はあったということを、きちんと認められれば、きちんと元のリスクも、皆さんの責任として、企業体としてこれを解決に、きちんと、貴行側の自己、自腹を切る、救済者に対して、主体の責任を認める、これをすべきである」
預金964億円減少の「真の意味」
AIの分析で特に重要だったのは、預金減少を単なる数字ではなく、社会からの信頼失墜の象徴として捉えた点でした。株主は預金964億円減少について、「一般の消費者から信頼されてない、とこれは業績的にも、数字に反映しているわけです」と指摘。これは事実上の市場による「不信任決議」だという認識を示しました。
レピュテーションリスクの実態化
AIの分析では、これまで「リスク」として語られてきたレピュテーション問題が、実際の財務数字として表面化していることを重視しました。つまり、もはや「将来のリスク」ではなく「現在進行形の損失」だという認識です。

被害者の「生の声」
AI分析と並んで強力だったのは、実際の被害者からの生の証言でした。「自殺すら考えた私自身の辛い気持ちっていうのは、やはり忘れられないんですよね」「このスルガ銀行さんがこんな6年も7年も問題を長期化しなければ、声を上げる必要ないんですよ、ないんです」「被害者代表として、会って、直接お話して話するような機会を設けていただきたい」などの生の声に対してスルガ銀行の経営層はどのようにうけとめたのでしょうか。
経営陣の沈黙
株主から飛び出したAI分析に対して、経営陣は実質的に意見を表明しませんでした。経営陣は「誠実に対応する」「全力で努める」といった従来型の形式的回答を繰り返すしかなく、具体的な反論や対案は提示されませんでした。株主総会を形式的な儀式として乗りきろうとする姿勢が感じられる対応だったといえます。
編集部の見解
今回のスルガ銀行株主総会で示されたAI活用。2025年現在、AIは独自に思考するものではなく、文脈を考えるとこうであろうと推論して回答を生成する仕組みで作動しています。そう考えると、各種資料から推論できるとAIが判断した内容は、いままでスルガ銀行が公的に発信してきた資料やメッセージから自然に推測できる取り組みであるといえます。それがスルガ銀行の経営陣にどう捉えられたかはさておき、内容が突飛な内容でなかった印象をもちました。
スルガ銀行の経営陣は、このAI分析結果をどう受け止め、どう行動するのか。おそらくスルガ銀行の姿勢は変わらないことでしょう。しかし誰もがそう期待する行動に反して、スルガ銀行が本音と建前を使い分け、組織的な不正融資に対する償いをおこなわず、不正融資被害者に譲歩しないまま強硬姿勢を貫くことで、社会的な制裁はますます強まることでしょう。
すでに個人からの預金残高は大幅に減少し、超党派の複数議員が幾度となく国会の審議会でスルガ銀行の不正について言及しています。
被害者団体の講義活動も6年以上に渡って展開されており、実ビジネスにも影響が出ていることでしょう。数百人の被害者の講義活動には、家族も含めると数千人の生活がかかっている以上、事態が改善しない限り自然と解消されるものではありません。
前代未聞の金融不祥事を起こしたスルガ銀行不正融資事件は6年半を過ぎてなおも混迷を深めています。