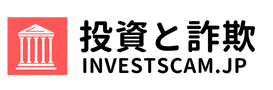大きなリターンが見込める投資以外にも、手元に残る利益を狙った投資もあります。ここでは最近また注目を集め始めた水耕栽培を少し拡大して、兼業農家となって節税することが可能かを検討します。
目次
農家の平均年収は240万円
「農業は国の根幹」とよく言われますが、食べるものを自ら作り出す農業は、形が変わっても絶対にニーズがなくならない事業と言えます。一方で外国産の安い農作物の輸入により厳しい価格競争にさらされてもいます。実際に1994年から2024年にかけて、日本の農業人口は大幅に減少しています。この期間における農業人口の変化は、主に高齢化や農業後継者の不足、都市部への移住、そして他産業への労働移動などが影響しています。
農業人口の変化(1994年から2024年)
1994年の農業人口
- 農業就業人口は約400万人を超えていました。
- 高齢化が進んでいたものの、当時はまだ農業従事者の数は多く、地域ごとに小規模な農家が多く存在していました。
2024年の農業人口
- 2024年における農業就業人口は100万人以下にまで減少していると予測されています。2022年の統計では、すでに農業人口は100万人を切っており、さらに減少が続いています。
- 農業従事者の高齢化が進み、平均年齢は67歳を超えています。また、若い世代が農業に従事する割合が非常に低いため、後継者不足が深刻化しています。
主な要因
- 高齢化: 農業人口の大部分を占めていた戦後世代が高齢化し、引退する一方で、若年層の農業従事者が少なくなっています。
- 都市化・工業化: 農村部から都市部への人口移動により、農業を続ける人が減少しました。
- 技術革新: 農業技術の進展により、一部の作業は機械化され、労働力が少なくても生産できるようになりましたが、その一方で農業就業者数自体は減少しています。
1994年から2024年の間に、農業人口はおよそ75%以上減少しているとみられ、このトレンドは今後も続く可能性があります。
こうした日本の農業の大幅な後退を埋めたのは輸入作物ですが、コロナのような世界情勢の悪化や戦争が発生すると海外から安価な農作物が入ってこない事態も想定されます。実際に2023年から2024年にかけて、気候変動によるコメの不作が発生したという噂が広がり、スーパーでコメが売り切れる事態も発生しました。コメ余りが問題になっていたはずがコメ不足に陥ったことで、数多くのお茶の間の主婦が右往左往したことでしょう。
今後、事業としての農業は今後、水耕栽培による工場生産やドローンやロボットを活用したIoT農業による生産性の向上などを迎えるなどして再編されていくことが想定されますが、お金を出しても買えなくなる可能性に関しては考えておく必要があります。
兼業農業による自営的な農業活動
こうした背景もあって、近年サラリーマンでも兼業農家になって、自分の食べる野菜をそだてようという動きや、副業として野菜を育て販売しようという動きが出てきました。
お小遣い稼ぎという面と自営的に農作物を確保するという2つの側面でこうした活動は意義があります。趣味の一環で取り組みを始める人も増えているわけですが、もう一歩進んで投資として考えるとしたら何をどこまで行えば、どの程度の利益が期待できるのでしょうか。
ワクワク広場や道の駅でトマトを販売
たとえばミニトマトを水耕栽培しているとします。道の駅や商業施設に入居している産直販売所であるワクワク広場などでは、スーパーと同じ、またはちょっと安い価格で販売されています。

たとえばミニトマト200gを330円で販売するとします。

ケースは30円ほどです。
ワクワク広場など直売場の場合、売上の10%から30%の間で手数料が発生します。また売り場で値引きされる場合もあります。
栽培方法によりますが、本格的な畑でなくても、水耕栽培のミニトマトの苗一株から数か月で40個から200個の収穫が期待できます。(幅があるのは生育条件によるものです。液肥を溶かした水分や日光、スペースがあれば水耕栽培で200個収穫できるケースもあります。逆に2リットルのペットボトルを加工した容器でこじんまり育成すると40個程度になるでしょう)
15個を330円で販売すると、一株で900円から4000円分生産できます。10株で9千円~4万円期待できるという事です。直売ならではの単価の良さで一定以上の売り上げを狙うことが可能です。
売り場によって販売力はかなり違うので、大きく変動するものの販売チャンスがある、商品陳列や補充だけで、特別なスキルも接客も不要な自動販売が可能と考えると副業や家族と協力して取り組めるビジネスチャンスといえそうです。
趣味と節税をかねて。ベランダ菜園するには
知り合いの税理士に確認したところ、農業を事業にしようとする際に、どの程度の活動実態があればよいのかに関して、明確な金額面での基準はないようです。また地域柄認められやすいエリアと難易度が高いエリアもあるということで、結局のところ、所轄の税務署の判断が全てといえます。
「所轄の税務署に聞く」のやり方
税理士は専門家ですが、判断を下すのは所轄の税務署の担当職員です。おそらく税理士はいままでの事例や自身の経験、所轄の税理士の傾向などを総合的に判断して回答してくれています。ではこの通り申告すればよいかというと、可能なだけで「通るかどうか」はわかりません。なぜなら申告を受け取り、判断するのは所轄の税務署の職員だからです。所轄外の職員に聞いても、判断する所轄の職員ではないので、所轄の職員の意見をきき言質を取るのが確実です。税務署には電話応対の履歴を管理する仕組みがあるので、電話で確認した日時や応対者、内容はメモされています。できるだけ穏便に低姿勢に、わからないと伝えながら温情を引き出す方向で相談を持っていくという、きわめてサラリーマン的な小市民スキルを駆使して有利な条件を引き出し、議事メモを作りましょう。これが実務的な言質のとり方です。
たとえば「”毎年20万円未満であれば、申告の必要がない”という基準はありますが、確定申告している人(自営業者、他の副業を実施している、医療費20万円超えで還付申告する、ふるさと納税を6つ以上の自治体に実施して還付を受ける等)であればこの基準とは関係なく、申告する場合は全ての事業収入を申告するのがルールとされていますので、農業も事業として申告することが可能です」という見解を税理士に示してもらったとします。
大半のケースではこの見解通りでよいのですが、不安が残る場合に所轄の職員のご意見を伺います。これはアポなしの電話で大丈夫です。
電話で何を確認するかですが、まずは「将来農業で起業したいので事業化を見据えて商材を検討し、設備を購入し、販売を行った。売上の目途が立ったので相談したい。まずは副業として申告が発生すると思うが正しい方法を教えてほしい」というような形で相談内容を伝えます。すると「帳簿が整備されている」「継続的、反復的に取り組まれている」「リスクを取って売上を得ることが目的の行動として取り組んでいる」「事業として取り組んでおり本気度がある」などの条件があれば、申請はできるというような説明をしていただけるはずです。そこで「現在の売上げが少なくても、農作物の栽培をおこない販売する以上、農業事業の売上として申請可能である」という言葉を引き出すように会話を運びましょう。ここでは農地を購入するわけではないので、最低耕作面積も、農業従事日数も関係ありませんが、念の為に「ベランダでの農作業は生き物相手なので毎日行っています、夜は情報収集や情報発信のためのほぼ毎日活動しています」と伝えるとよいかもしれません。
実際にベランダで水耕栽培を始めるには
youtubeで水耕栽培を調べると、ペットボトルや100均で購入できる材料で始めることができる家庭菜園向きの水耕栽培の実演が複数ヒットすると思います。どれでも良いので、一度通しで見てください。書籍がよい方は、園芸のコーナーに行けば水耕栽培に関する本がおいてあります。人気のテーマなので図書館などにもあるかもしれません。
Amazonで水耕栽培と検索すると水耕栽培キットも販売されています。卓上に設置し、LEDライトもついているような装置もあれば、塩ビの筒を複数つなげた栽培装置に水をくみ上げるポンプが付属したキットも見かけることができるでしょう。
実際に塩ビの水耕栽培キットを使って育てたのですが、複数の種類を同じ水耕栽培キットの中で育てると生育が悪くなるようです。バジルのように強い植物はそれでも育ちましたが、育ちが小ぶりでした。小ぶりとは言ってもワクワク広場で100円から200円で販売されている根っこつきのバジルと同じくらいには育ちますので、1万円程度の売り上げが期待できるようです。春から秋にかけて成長するので、何度もカットして出荷すれば定期収入になりそうです。
ミニトマトのように枝ぶりが茂げる植物は塩ビ筒を三階建てで運用するキットには不向きのようですが、バケツで育てていたyoutuberは一株を育てて、ひと夏で1200個以上の収穫をしたといいます。もし20個300円で販売できれば、1万8000円の売り上げになります。自分の家で消費する分を除いても数本育てれば趣味と実益を兼ねた小規模な商いになりそうです。