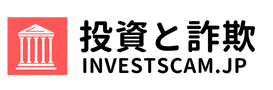目次
はじめに:政治的混乱が投資環境に与える影響
2025年10月、世界の投資環境は予想以上の混乱に直面している。米国ではドナルド・トランプ氏が第47代大統領として返り咲きを果たし、1月20日に第二次政権をスタートさせてから9ヶ月が経過したが、10月1日から連邦政府の一部閉鎖(シャットダウン)が始まり、現在も継続中である。一方、日本では10月21日に高市早苗氏が第104代内閣総理大臣に就任し、憲政史上初の女性首相が誕生したばかりだ。
米国の政府閉鎖は約7年ぶりであり、上院で共和党と民主党の対立が解消されないまま、新会計年度に突入したことが原因である。民主党は医療保険補助金(オバマケア)の延長を要求し、共和党はこれを拒否。上院でつなぎ予算案を可決するには60票が必要だが、共和党は53議席しか持たず、民主党の協力が不可欠な状況で膠着状態に陥っている。
さらに深刻なのは、トランプ政権が政府閉鎖を利用して連邦職員の大量解雇を計画していることである。行政管理予算局(OMB)は各省庁に対し、「優先的ではない」事業の人員削減計画策定を指示しており、約75万人の連邦職員が一時帰休となる可能性に加えて、恒久的な解雇も示唆されている。政府閉鎖が35日間続いた場合、実質GDPは前期比年率0.6%下振れるとの試算もあり、経済への悪影響が懸念されている。
トランプ政権は発足当初、政府効率化省(DOGE)を通じた大規模な歳出削減を掲げたが、イーロン・マスク氏が5月末に特別政府職員の任期満了により政権を離脱するなど、政策実行には大きな紆余曲折があった。マスク氏は政権離脱時に「財政赤字を拡大する減税法案には失望した」と述べ、トランプ大統領との関係も冷却化している。そして現在、議会での予算成立のめどは立たず、政府閉鎖は長期化の様相を呈している。
日本では高市政権が発足直後であり、防衛力強化と経済安全保障を柱とする政策の具体化はこれからである。少数与党という不安定な政治基盤を抱える中、米国の政府閉鎖という同盟国の混乱が、日本の政策運営にも影響を及ぼす可能性がある。
本稿では、この政治的混乱と高い不確実性の中で、各資産クラスがどのような影響を受け、投資家は今後いかなる戦略を採用すべきかを分析する。政策の不確実性は、当初の予想に反して低下するどころか、むしろ高まっている状況にあることを前提に、リスク管理を重視した投資アプローチを提示する。
資産クラス別影響分析の全体像
両政権の政策が各資産クラスに与える影響は多層的である。以下の分析マトリックスは、主要な政策要因が各資産クラスに及ぼす影響度を視覚化したものだ。
画像を表示
この影響度マトリックスから、トランプ政権の政策は米国株式と商品市場に強い正の影響を与える一方、インフレ圧力を通じて債券市場には負の影響をもたらすことが読み取れる。高市政権の政策は日本株式、特に防衛関連セクターに最も強い正の影響を与え、オルタナティブ投資にも追い風となる。防衛費増額は両国の株式市場と、特にプライベートエクイティを含むオルタナティブ投資に大きな機会をもたらす。
一方、インフレリスクは両国の債券市場に共通の課題となり、慎重な金利動向の見極めが必要となる。貿易摩擦の激化は為替市場のボラティリティを高める要因であり、為替ヘッジ戦略の重要性が増している。
株式市場:セクター選別が成否を分ける時代
米国株式市場の展望:政府閉鎖がもたらす不確実性
第二次トランプ政権下の米国株式市場は、政権発足から10ヶ月を経て、予想外の政治的混乱に直面している。10月1日から始まった政府閉鎖は、2018年末から2019年初頭にかけての35日間の閉鎖以来、約7年ぶりの事態である。今回の閉鎖は、単なる予算執行の一時停止にとどまらず、トランプ政権が連邦職員の大量解雇を計画しているという点で、過去の閉鎖とは性質が異なる。
政府閉鎖の直接的な影響として、雇用統計などの重要な経済指標の発表が遅延する可能性が高い。労働統計局(BLS)は業務を停止しており、10月末の連邦公開市場委員会(FOMC)での金融政策判断に支障が生じる懸念がある。経済データの欠如は市場の不確実性を高め、投資判断を困難にする要因となる。
株式市場への影響は、政府閉鎖の期間に大きく左右される。議会予算局(CBO)の試算によれば、閉鎖が35日間続いた場合、実質GDPは前期比年率0.6%下振れする可能性がある。さらに、連邦職員の大量解雇が実施されれば、その影響は一層深刻化し、GDP押し下げ効果は1.0%程度に達する可能性もある。消費の減速や企業活動の停滞を通じて、株式市場には下押し圧力がかかることが予想される。
世論調査では、政府閉鎖の責任について、共和党にあるとする回答が47%、民主党にあるとする回答が30%となっており、有権者の不満は与党に向かう傾向が見られる。2026年の中間選挙を控えて、この政治的混乱が長期化すれば、トランプ政権の支持率低下を通じて市場心理を冷やす可能性がある。
セクター別に見ると、政府閉鎖の影響を直接受ける防衛関連企業や政府調達に依存する企業は、短期的には受注の遅延や支払いの停止といった問題に直面する。一方、民間需要が主体の半導体、医療機器、化学などの産業は、相対的に影響が限定的である。ただし、経済全体の減速懸念が高まれば、すべてのセクターが売り圧力にさらされる可能性がある。
インフラ関連企業も、政府支出の停止により短期的な逆風を受ける。公共インフラ整備プロジェクトの発注が遅延すれば、関連企業の業績見通しは悪化する。ただし、政府閉鎖が解消され、補正予算が成立すれば、遅延した支出が一気に執行される可能性もあり、その時期を見極めることが重要となる。
現時点での投資戦略としては、政府閉鎖の長期化リスクを織り込み、防御的なポジショニングを優先すべきである。現金比率を通常より高めに保ち、市場の急変に対応できる体制を整える。政府閉鎖が短期間で解消されれば、売り込みは買い場となる可能性があるが、長期化すれば本格的な調整局面に入る覚悟が必要である。
日本株式市場の構造変化
高市政権の発足は、日本株式市場に新たなダイナミズムをもたらしている。最も顕著な影響が見られるのが防衛関連セクターである。高市首相は防衛費のGDP比2%への引き上げ目標を2027年度から2025年度中に前倒しし、さらに2%超への引き上げも視野に入れている。この政策転換は、長年低迷してきた日本の防衛産業に大きな追い風となる。
防衛産業株への投資機会は多層的である。直接的な恩恵を受けるのは、三菱重工業や川崎重工業、IHIといった総合重工メーカーだが、電子機器や通信システム、サイバーセキュリティを手がける企業にも波及効果が及ぶ。特に注目すべきは、軍民両用技術いわゆるデュアルユース技術への投資拡大である。高市政権はこの分野への戦略的投資を通じて、防衛力強化と経済成長を同時に実現する方針を打ち出している。
経済安全保障の観点からは、半導体や先端材料、AI技術といった分野への政府支援が強化される見通しだ。これらの分野では、中国への技術流出を防ぐための規制強化と同時に、国内企業の技術開発支援が行われる。半導体製造装置メーカーの東京エレクトロンや、半導体材料を手がける信越化学工業、JSRなどは、この政策の恩恵を受ける立場にある。
高市政権が掲げる「責任ある積極財政」は、内需関連株にも追い風となる。物価高対策を最優先課題とする一方で、戦略的な財政出動を通じた経済の好循環実現を目指しており、建設、不動産、小売、サービス業などの内需セクターに資金が流れる可能性がある。特にインフラ老朽化対策や防災関連の公共投資は、地方経済の活性化にも寄与する形で展開される見込みだ。
ただし、高市政権は自民党と日本維新の会による連立政権であり、衆参両院で少数与党という不安定な政治基盤を抱えている。政策実行には野党との協調が不可欠であり、財政支出の規模や内容が当初の構想から修正される可能性がある。この政治的不確実性は、短期的には市場のボラティリティを高める要因となる。
セクター別投資魅力度の詳細分析
両政権の政策を踏まえた各セクターの投資魅力度を定量的に評価すると、以下のような構図が浮かび上がる。
画像を表示
この分析から明らかなように、防衛産業は日本市場で最高の魅力度を示している。高市政権の防衛費GDP比2%超への引き上げ方針と、デュアルユース技術への戦略的投資により、このセクターは今後数年にわたって高成長が見込まれる。半導体セクターも両国で高い評価を受けており、経済安全保障の観点からの政府支援と、AI需要の拡大という二つの追い風を受けている。
インフラセクターは米国市場でより高い評価となっているが、これはトランプ政権の国内生産回帰政策に伴う大規模なインフラ整備需要を反映している。一方、日本のインフラセクターも防災対策や首都機能バックアップという高市政権の重点政策により、堅調な成長が期待される。
エネルギーセクターは米国市場で相対的に魅力度が高く、トランプ政権の化石燃料産業への規制緩和が追い風となる。日本市場でのエネルギーセクターの評価が低いのは、再生可能エネルギーへの転換圧力と、化石燃料への依存度低減政策が継続されるためである。
日米株式市場の連動性
両政権の政策には、日米同盟強化という共通の基盤がある。トランプ大統領は就任後早い段階で日本を訪問する予定であり、防衛協力や経済安全保障での連携が確認される見通しだ。この日米協力の深化は、両国の株式市場にプラスの影響をもたらす。
特に防衛産業では、日米企業の提携や技術協力が加速する可能性が高い。米国の防衛関連企業と日本企業の合弁事業や、共同開発プロジェクトが増加すれば、両国の関連企業に投資機会が生まれる。また、半導体やAI、量子コンピューティングといった先端技術分野でも、日米の産学官連携が強化される見込みだ。
日本企業による対米投資も活発化するだろう。日本は2019年以降、5年連続で対米直接投資残高の国別首位を維持しており、雇用創出でも英国に次ぐ2位の地位にある。トランプ政権が求める対米投資拡大と雇用創出において、日本は既にトップランナーの地位にあり、この実績を背景に日米経済関係は深化する方向にある。
債券市場:金利動向の読みが重要に
米国債券市場の展望:財政リスクの顕在化
トランプ政権の財政政策と政府閉鎖は、2025年10月現在、米国債市場に深刻な影響を及ぼしている。政府閉鎖の長期化は、米国の財政ガバナンスに対する信認を損なう要因となり、長期金利の上昇圧力となる可能性がある。
政府閉鎖が35日間続いた場合、GDPが約110億ドル減少するとの試算がある中、財政赤字はさらに拡大する見込みだ。トランプ政権が推進する大型減税法案は、今後10年間で10.4兆ドルの財源が必要とされるが、政府閉鎖により歳出削減の目処が立たず、財政規律への懸念が高まっている。
イーロン・マスク氏が率いた政府効率化省(DOGE)は、連邦職員約26万人の削減という成果を上げたものの、マスク氏は5月末に政権を離脱し、その際に「財政赤字を拡大する減税法案には失望した」と批判した。DOGEによる歳出削減の取り組みは継続されているものの、社会保障関連の義務的経費や国債の利払費など、削減が困難な支出が大半を占めるため、財政赤字の大幅な縮小には至っていない。
現在の政府閉鎖は、財政支出の一時停止により短期的には財政赤字を抑制する効果があるが、閉鎖解消後の補正支出や経済への悪影響による税収減を考慮すれば、中長期的には財政状況を悪化させる要因となる。市場は、米国の財政運営能力に対する疑念を強めており、ドルの信認低下とともに、長期国債の利回り上昇圧力が高まっている。
一方で、政府閉鎖による経済活動の鈍化は、インフレ圧力を抑制する効果がある。関税政策の影響も、当初の懸念ほど顕在化していないため、FRBが金融引き締めを急ぐ必要性は低下している。むしろ、政府閉鎖の長期化が景気後退リスクを高めれば、FRBは追加利下げを検討せざるを得なくなる可能性もある。
債券投資戦略としては、現時点では中期債を中心とした慎重なポジショニングが適切である。政府閉鎖が短期間で解消されれば、財政不安は後退し、長期金利は低下する可能性がある。一方、閉鎖が長期化し、財政ガバナンスへの懸念が強まれば、長期金利は上昇圧力を受ける。この二つのシナリオを見極めながら、デュレーションを調整する柔軟な対応が求められる。
また、政府閉鎖中は経済指標の発表が遅延するため、市場の不確実性が高まる。この環境下では、流動性の高い国債を中心に保有し、急激な市場変動に対応できる体制を維持することが重要である。
日本債券市場の変化
日本の債券市場は、日本銀行の金融政策正常化プロセスと高市政権の財政政策という二つの要因に影響を受ける。日銀は2024年からマイナス金利政策を解除し、イールドカーブコントロールの修正を進めてきたが、高市政権下でこのプロセスがどう進展するかが注目される。
高市政権の「責任ある積極財政」は、一見すると財政拡大を意味するように見えるが、その実態は成長投資を通じた税収増加を目指すものである。防衛力強化や経済安全保障関連の支出は増加するものの、無秩序な財政拡大ではなく、投資リターンを意識した戦略的支出が志向されている。この方針が実際に実行されれば、日本国債の信認は維持される可能性が高い。
ただし、少数与党という政治状況は、予算編成プロセスに不確実性をもたらす。野党との協議が難航すれば、財政政策の規模や内容が当初計画から変更される可能性がある。また、連立を組む日本維新の会は財政規律を重視する傾向があり、自民党の一部議員とは異なる立場を取ることもある。この政治的ダイナミクスは、国債発行計画や財政収支見通しに影響を及ぼす可能性がある。
日本国債への投資戦略としては、中期ゾーンの魅力が相対的に高まっている。短期金利は日銀の政策金利に連動して上昇する一方、長期金利は財政政策の行方を織り込んで変動する。この環境下では、3年から7年程度の中期債が、金利変動リスクとリターンのバランスが取れた投資対象となる。
社債市場では、防衛関連企業や経済安全保障に関わる企業の起債が増加する見込みだ。これらの企業は政府からの受注増加が見込まれるため、信用リスクは相対的に低い。ただし、防衛産業への投資を避けるESG投資家の存在を考慮すると、発行企業によっては投資家層が限定される可能性がある。
為替市場:ドル円相場の新たな均衡点
ドル高圧力とその持続性
トランプ政権の政策は、短期的にはドル高要因となる。関税引き上げは米国への資金還流を促し、国内生産回帰は米国内での投資需要を高める。また、インフレ懸念が高まれば、FRBは金融引き締め姿勢を維持せざるを得ず、高金利がドルを支える構図となる。
しかし、中長期的にはドル安圧力も無視できない。巨額の財政赤字と経常赤字という「双子の赤字」は、ドルの信認を徐々に低下させる要因となる。また、トランプ大統領自身が製造業の競争力維持のために弱いドルを望む発言をすることもあり、政権の為替政策には不確実性が伴う。
円の立ち位置と日本の金融政策
日本円については、高市政権の政策が強い影響を与える。積極財政は一般的には通貨安要因となるが、高市政権の場合は単純な財政拡大ではなく、成長投資を志向している点が異なる。防衛力強化や経済安全保障への投資が経済成長につながれば、むしろ円高要因となる可能性がある。
日銀の金融政策正常化も円相場を左右する。利上げペースが市場予想を上回れば円高圧力が強まり、逆に慎重な姿勢が続けば円安圧力が残る。高市政権と日銀の政策協調がどのように機能するかが、円相場の方向性を決める重要な要素となる。
ドル円の投資戦略
為替市場では、2025年を通じてドル円相場が140円から155円程度のレンジで推移する可能性が高い。年前半はトランプ政権の政策不確実性からドル高円安に振れやすく、年後半は政策の明確化と日銀の正常化進展により円高方向に調整する展開が予想される。
為替ヘッジの判断は、投資家の立ち位置によって異なる。米国株式への投資を検討する日本の投資家にとっては、年前半のドル高局面では為替ヘッジなしでドル資産を保有することが有利となる可能性が高い。一方、年後半に向けては部分的なヘッジを検討する余地がある。逆に米国投資家が日本株に投資する場合は、円高リスクを考慮したヘッジ戦略が重要となる。
商品市場:資源ナショナリズムの時代
エネルギー市場の地殻変動
トランプ政権のエネルギー政策は、化石燃料産業への規制緩和を柱としている。パリ協定からの離脱姿勢や、国内での石油・ガス採掘規制の緩和は、短期的には原油・天然ガス価格の下押し圧力となる。米国のエネルギー生産能力が拡大すれば、世界のエネルギー需給バランスに大きな影響を与える。
しかし、中東情勢の不安定化や、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化は、エネルギー価格の上昇リスクとして残る。トランプ政権の外交政策がこれらの地政学リスクにどう対処するかが、エネルギー価格の行方を左右する。また、中国経済の減速は世界のエネルギー需要を押し下げる要因となり、価格の上値を抑える。
エネルギー投資戦略としては、地政学リスクのヘッジとして一定のエネルギー関連資産を保有しつつ、価格の大きな変動を利用した機動的な売買が有効となる。原油価格が70ドルを下回る局面では買い、90ドルを超える局面では売るといった、レンジ取引の発想が適している。
貴金属市場:金の輝きは続くか
金価格は2024年から2025年にかけて史上最高値圏で推移している。この背景には、地政学リスクの高まりや、中央銀行による金購入の増加がある。トランプ政権と高市政権の誕生は、政策の不確実性を通じて金需要を支える要因となる。
特に注目すべきは、中央銀行の金購入動向である。米中対立の深刻化を受けて、多くの新興国中央銀行が外貨準備の多様化を進めており、金の保有比率を高めている。この傾向は今後も続くと予想され、金価格の下値を支える。
ただし、金利の動向には注意が必要だ。米国の実質金利が上昇すれば、利息を生まない資産である金の魅力は相対的に低下する。FRBの金融政策が引き締め方向に傾けば、金価格は調整を余儀なくされる可能性がある。
金投資については、ポートフォリオ全体の5%から10%程度を金関連資産に配分するのが適切だろう。金現物、金ETF、金鉱株など、投資手段は多様化させることでリスクを分散できる。価格が大きく上昇した局面では利益確定を検討し、調整局面では買い増すという方針が、長期的なリターン向上につながる。
レアメタル・半導体材料:経済安全保障の焦点
経済安全保障の観点から、レアメタルや半導体製造に必要な特殊材料への注目度が高まっている。中国がこれらの資源の供給を戦略的に管理していることから、日米両国は供給源の多様化を急いでいる。
リチウム、コバルト、レアアース、ガリウムなどの戦略的鉱物資源は、電気自動車や再生可能エネルギー、先端半導体の製造に不可欠である。トランプ政権は国内での鉱物資源開発を促進する方針を打ち出しており、高市政権も資源確保を経済安全保障の重要課題と位置づけている。
これらの資源への投資は、直接的な商品投資よりも、関連する鉱山会社や精錬企業への株式投資を通じて行うのが現実的である。オーストラリアやカナダの資源会社は、中国以外の供給源として戦略的価値が高まっており、長期的な投資対象として魅力がある。
不動産市場:地政学が変える立地価値
米国不動産市場の二極化
米国の不動産市場は、トランプ政権の政策によって地域間の格差が拡大する可能性がある。国内生産回帰を推進する政策は、製造業の集積地となる地域の不動産需要を高める。特にテキサス州、アリゾナ州、ノースカロライナ州など、ビジネス環境が良好で労働コストが比較的低い地域が恩恵を受ける。
一方、移民抑制政策は建設労働力の不足を通じて、不動産開発コストを押し上げる可能性がある。これは新規供給の抑制要因となり、既存物件の価値を相対的に高める効果がある。ただし、高金利環境が続けば、不動産価格の上昇は抑制される。
商業用不動産では、オフィス市場の回復が鈍い一方、物流施設や データセンターへの需要は堅調に推移している。国内生産回帰に伴う物流需要の増加や、AI技術の発展によるデータセンター需要の拡大は、これらのセクターへの投資機会を生み出している。
日本不動産市場の新展開
高市政権の政策は、日本の不動産市場に独特の影響を与える。防衛関連施設の整備や、経済安全保障に関わる研究開発拠点の建設は、特定地域の不動産需要を高める。また、積極財政による公共投資の拡大は、インフラ整備が進む地域の不動産価値を押し上げる。
東京都心部の商業用不動産は、海外投資家からの需要が根強く、価格は高止まりしている。円安が続けば外国人投資家にとっての割安感が強まり、さらなる資金流入が期待できる。ただし、オフィス需要は在宅勤務の定着により構造的な変化に直面しており、立地や物件の質による選別が進んでいる。
住宅市場では、金利上昇の影響が徐々に顕在化している。日銀の金融政策正常化に伴う住宅ローン金利の上昇は、住宅購入意欲を減退させる要因となる。一方、高市政権の賃上げ支援策が功を奏し、実質賃金の改善が進めば、住宅需要を下支えする効果がある。
不動産投資信託への投資は、個別物件への直接投資に比べて流動性が高く、分散投資も容易である。防衛施設周辺の商業施設や、物流施設、データセンターに投資するREITは、政策的な追い風を受ける可能性が高い。配当利回りが4%を超える水準であれば、長期保有に適した投資対象となる。
オルタナティブ投資:新時代の資産防衛
プライベートエクイティと防衛産業
トランプ政権と高市政権の防衛力強化方針は、プライベートエクイティ市場に新たな投資機会を生み出している。上場していない防衛関連企業や、軍民両用技術を開発するスタートアップへの投資需要が高まっており、これらの企業を対象とするファンドが組成されている。
トランプ政権は発足当初、政府効率化省(DOGE)を通じた大規模な歳出削減を掲げたが、実際には連邦職員削減にとどまり、防衛予算は維持されている。むしろ、イーロン・マスク氏が5月末に政権を離脱した後も、防衛・安全保障分野への投資は継続されており、民間企業が軍事技術開発において重要な役割を果たす構造は変わっていない。
特に注目されるのが、サイバーセキュリティ、ドローン技術、AI防衛応用、宇宙関連技術などの分野である。これらの領域では、民間企業が軍事技術の開発において重要な役割を果たすようになっており、政府からの開発支援や調達が期待できる。
プライベートエクイティへの投資は、一般的に最低投資額が高く、資金の拘束期間も長いが、上場株式では得られない高いリターンの可能性がある。ただし、流動性リスクや情報の非対称性には十分な注意が必要であり、投資家は自身のリスク許容度と投資期間を慎重に検討すべきである。
インフラ投資の戦略的重要性
両政権ともインフラ整備を重要政策として位置づけており、インフラ投資は安定したキャッシュフローと長期的なリターンが期待できる資産クラスとして魅力を増している。トランプ政権は国内のインフラ老朽化対策を推進し、高市政権は防災インフラの強化と首都機能のバックアップ体制構築を進める方針である。
インフラ投資の対象は、道路や橋梁といった伝統的なものから、5G通信網、データセンター、再生可能エネルギー施設など、デジタル・エネルギーインフラへと拡大している。これらの新世代インフラは、経済安全保障の観点からも戦略的重要性が高く、政府の支援を受けやすい。
インフラファンドやインフラ債券を通じた投資は、株式市場の変動に左右されにくく、ポートフォリオの安定性向上に寄与する。ただし、政策変更リスクや規制リスクには注意が必要であり、投資対象の選定には専門的な知識が求められる。
暗号資産:規制環境の変化に注目
トランプ政権は暗号資産に対して比較的前向きな姿勢を示しており、規制の明確化を通じて市場の健全な発展を促す方針である。この政策転換は、暗号資産市場に資金流入をもたらす可能性がある。ビットコインやイーサリアムといった主要暗号資産は、規制の明確化を好感して上昇する場面も見られる。
ただし、暗号資産市場は依然として投機性が高く、価格変動が激しい。ポートフォリオ全体の数パーセント程度に留めるのが賢明であり、失っても生活に支障がない範囲での投資に限定すべきである。
総合投資戦略:不確実性の中で成果を上げる
ポートフォリオ構築の基本方針
トランプ政権と高市政権という二つの新政権が同時に始動する2025年は、政策の不確実性が高い年である。このような環境下では、特定の資産クラスやセクターに過度に集中するのではなく、分散投資を基本としつつ、両政権の政策方向性に沿った戦略的な傾斜配分を行うことが重要となる。
画像を表示
上図は、リスク許容度の異なる投資家向けの推奨ポートフォリオ配分を示している。保守的なポートフォリオでは、債券を45%と最大の配分とし、株式を35%、オルタナティブ投資を10%、現金を10%とする構成が適切である。この配分は、政策の不確実性が高い環境下で、資産の安定性を重視する投資家に適している。
一方、積極的なポートフォリオでは、株式への配分を60%まで高め、債券を25%、オルタナティブ投資を12%、現金を3%とする。この配分は、両政権の成長志向政策から最大限の恩恵を受けることを目指す投資家向けである。ただし、株式投資の内訳として、防衛関連、経済安全保障関連、インフラ関連に重点を置き、政策の追い風を受けるセクターを選別することが重要である。
株式投資では、全体の50%から60%を配分し、その中で防衛関連、経済安全保障関連、インフラ関連に重点を置く。米国株式と日本株式の配分比率は、為替見通しや各市場のバリュエーションを考慮して調整するが、概ね6対4から7対3程度が適切だろう。
債券投資は、ポートフォリオの安定性を確保するために30%から40%程度を配分する。金利変動リスクを考慮し、デュレーションは中程度に抑え、信用リスクの低い国債や高格付け社債を中心とする。年後半に向けては、政策の不確実性低下に伴い、徐々にリスクを取る余地が生まれる。
オルタナティブ投資は、ポートフォリオの10%から15%程度を上限とする。プライベートエクイティ、インフラ投資、商品、不動産投資信託などに分散し、流動性を確保しながらリターンの向上を図る。暗号資産への投資は、極めて限定的な範囲に留めるべきである。
時間軸別の投資アプローチ:政府閉鎖下での戦略
2025年10月から2026年にかけての投資環境は、米国政府閉鎖の帰趨に大きく左右される。以下の分析は、現在進行中の政治的混乱を前提としたものである。
画像を表示
2025年第4四半期(現在):高リスク・低リターンの局面
10月から始まった政府閉鎖により、投資環境は極めて不確実性が高い状態にある。当初の予測では、この時期は政策不確実性が低下し、リスクレベルは中程度、期待リターンは上昇傾向にあるはずだったが、現実は大きく異なる展開となっている。
政府閉鎖が短期間(2〜3週間以内)で解消されれば、市場は急速に回復し、売り込みは絶好の買い場となる可能性がある。しかし、2018-2019年の前回閉鎖が35日間続いたことを考えれば、長期化のシナリオも十分に想定すべきである。特に、トランプ政権が連邦職員の大量解雇を計画しているという点で、今回の閉鎖は過去とは性質が異なり、より深刻な経済的影響をもたらす可能性がある。
現時点での投資戦略は、防御一辺倒とすべきである。現金比率を30%以上に引き上げ、市場の急変に対応できる体制を整える。株式ポートフォリオの中では、政府支出に依存しない民需主体のセクター(テクノロジー、ヘルスケア、消費財)を相対的に重視し、政府調達に依存する防衛関連やインフラ関連は比率を下げる。
2025年末から2026年第1四半期:シナリオ分岐点
政府閉鎖がいつ解消されるかにより、年末から年初にかけての投資環境は大きく二つのシナリオに分かれる。
楽観シナリオでは、11月中に政府閉鎖が解消され、その後つなぎ予算が成立、遅れていたトランプ減税法案も議会を通過する。この場合、抑制されていた政府支出が一気に執行され、減税効果とあわせて経済は回復軌道に戻る。株式市場は大きく上昇し、リスク資産への回帰が進む。このシナリオでは、閉鎖中に売り込まれた防衛関連やインフラ関連株が急反発する可能性が高い。
悲観シナリオでは、政府閉鎖が年末まで続き、2026年に入っても解消の目処が立たない。連邦職員の大量解雇が実行され、経済活動は大幅に縮小する。株式市場は本格的な調整局面に入り、安全資産への逃避が加速する。このシナリオでは、金や国債といった伝統的な安全資産が相対的に堅調に推移する。
投資家は、この二つのシナリオのいずれが実現するかを日々の政治動向から判断し、ポジションを機動的に調整する必要がある。政府閉鎖解消の兆しが見えた時点で、リスク資産への配分を段階的に引き上げる準備をしておくべきである。
2026年第2四半期以降:回復の道のりは険しい
仮に政府閉鎖が2026年初頭までに解消されたとしても、その経済的影響は数ヶ月にわたって残る。消費の回復、企業の投資再開、雇用の正常化には時間がかかり、第2四半期以降も景気回復のペースは鈍いものとなる可能性が高い。
また、2026年11月には米国中間選挙が予定されており、政府閉鎖を招いた政治的対立が選挙戦でどう評価されるかが、その後の政策運営を左右する。共和党が議会の支配を失えば、トランプ政権の政策実行力はさらに低下し、政治的混乱は長期化する。
この時期の投資戦略としては、経済回復の実態を経済指標で確認しながら、慎重にリスクテイクを拡大していくアプローチが適切である。政治リスクは引き続き高い状態が続くため、ポートフォリオの分散を徹底し、特定のセクターや地域への過度な集中を避けるべきである。
長期的には、両政権の政策が構造的に変化させる産業や地域に注目する。防衛産業の復権、経済安全保障の強化、サプライチェーンの再編といった変化は、一時的なものではなく、今後数年から十年にわたって続く可能性がある。これらの構造変化を先取りした投資が、長期的なリターンの源泉となる。
リスク管理の重要性
2025年の投資環境で最も重要なのは、リスク管理である。政治的不確実性が高い環境では、想定外の事態が発生する可能性が常にある。ポートフォリオの定期的な見直しと、リスク許容度を超えないポジション管理が不可欠である。
特に注意すべきリスクは、米中対立の激化、関税政策の予想外の展開、インフレの再加速、金利の急上昇、政治的混乱などである。これらのリスクシナリオに対する備えとして、一定の現金ポジションを維持し、市場急変時に機動的に対応できる体制を整えておくことが重要である。
また、過度な楽観論や悲観論に惑わされず、冷静な判断を維持することが求められる。メディアやSNSの情報は、しばしば極端な見方に偏りがちである。信頼できる情報源から多角的に情報を収集し、自身の投資方針と照らし合わせて判断する姿勢が、成功への道となる。
結論:不確実性の中での投資判断
2025年10月現在、投資環境は当初の予想とは大きく異なる展開を見せている。トランプ政権は発足から9ヶ月が経過したが、10月1日から始まった政府閉鎖により、政策の不確実性は低下するどころか、むしろ危機的な水準に達している。高市政権は発足直後であり、米国の政治的混乱が日本の政策運営にも影響を及ぼす可能性がある。
米国政府閉鎖は、共和党と民主党の対立が解消されず、解決の目処が立っていない。トランプ政権が連邦職員の大量解雇を計画していることから、今回の閉鎖は過去とは性質が異なり、経済への影響はより深刻化する可能性がある。市場は、米国の財政ガバナンスと政治的機能不全に対する懸念を強めており、ドルの信認低下とともに、投資家のリスク回避姿勢が強まっている。
イーロン・マスク氏は5月末に政権を離脱し、トランプ大統領の減税法案を「財政赤字を拡大する」と批判するなど、当初期待された政府効率化の取り組みは計画通りには進んでいない。そして現在、予算成立のめどが立たない状況は、財政規律への懸念を一層高めている。
現時点での投資指針
このような極めて不確実性の高い環境下では、以下の三つの原則に基づいた投資戦略が不可欠である。
第一に、リスク管理を最優先することである。現金比率を通常より高めに保ち(ポートフォリオの30%以上)、市場の急変に対応できる流動性を確保する。政府閉鎖が短期間で解消されれば買い場となるが、長期化すれば本格的な調整局面に入る可能性がある。いずれのシナリオにも対応できる柔軟な資産配分が求められる。
第二に、政治動向を日々注視し、機動的にポジションを調整することである。政府閉鎖解消の兆しが見えた時点で、段階的にリスク資産への配分を引き上げる準備をしておく。一方、閉鎖が長期化する兆候が強まれば、さらなる防御的姿勢への転換を躊躇してはならない。経済指標の発表遅延により、通常の経済分析が困難になっている現状では、政治ニュースへの感度を高める必要がある。
第三に、分散投資を徹底することである。米国株式への集中投資は避け、日本株式、欧州株式、新興国株式など、地域的な分散を図る。また、資産クラスについても、株式だけでなく、債券、金、不動産投資信託など、相関の低い資産を組み合わせることでポートフォリオ全体の変動を抑制する。
セクター戦略の見直し
当初想定していた防衛関連、インフラ関連への重点配分は、政府閉鎖により見直しが必要である。これらのセクターは政府支出に直接依存するため、短期的には大きな逆風を受ける。一方、民需主体のテクノロジー、ヘルスケア、消費財セクターは、相対的に影響が限定的である。
ただし、政府閉鎖が解消され、補正予算が成立すれば、遅延した政府支出が一気に執行される可能性があり、その時点で防衛関連やインフラ関連株は大きく反発する可能性がある。したがって、これらのセクターを完全に避けるのではなく、比率を抑えながらも一定の持ち高を維持し、反転の兆しを捉える準備をしておくことが重要である。
長期的視点の維持
政府閉鎖という短期的な混乱に惑わされず、長期的な構造変化を見失わないことも重要である。防衛産業の復権、先端技術への戦略的投資、サプライチェーンの再編、経済安全保障の強化といった趨勢は、政府閉鎖が解消されれば再び投資テーマの中心に戻ってくる。
高市政権の日本では、防衛力強化と経済安全保障を柱とする政策が本格化する。少数与党という政治基盤の不安定さはあるものの、これらの政策方向性は超党派の支持を得やすく、実現可能性は高い。日本株式、特に防衛関連、半導体、経済安全保障関連のセクターは、中長期的な投資対象として魅力を維持している。
最後に
2025年10月という時点は、当初予想していた「政策の不確実性が低下し、具体的な投資機会が見えてきた段階」ではなく、「予期せぬ政治的混乱により、投資家の忍耐とリスク管理能力が試される段階」となっている。この困難な状況を乗り越えるためには、冷静な判断と柔軟な対応、そして長期的視点の維持が不可欠である。
危機は機会でもある。政府閉鎖が解消された時点で、市場は大きく反発する可能性が高い。その機会を逃さないためにも、現在は防御的姿勢を維持しながら、反転のタイミングを見極める準備を怠らないことが重要である。変化を恐れず、しかし慎重に、そして戦略的に。この姿勢が、混乱期の投資成功への鍵となる。